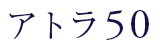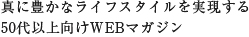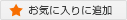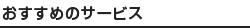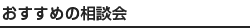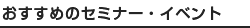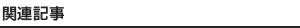あなたの気になる疑問お寄せ下さい!
あなたの気になる疑問お寄せ下さい!
投資、相続、住まい、法律、健康、ファッションなど、
専門家に質問したいことがありましたら、お気軽にお寄せください!
お寄せいただいた質問や、専門家の回答は、
あなたの個人情報を特定できない形で、Q&Aコラムとして掲載させて頂きます。
また、質問の内容によってはお答えできない場合がある事をご了承ください。
質問例
- (相続)息子の株損失を肩代わりした贈与を節税したい
- (メイク)登山で紫外線対策もオシャレもしたい山ガール向け50代さっぱりメイク
- (整理収納)会社でデスクを整理整頓してキレイに見えるコツ
- (運動)慢性的なテクノストレスを改善する顔まわりの指圧方法
- 質問内容